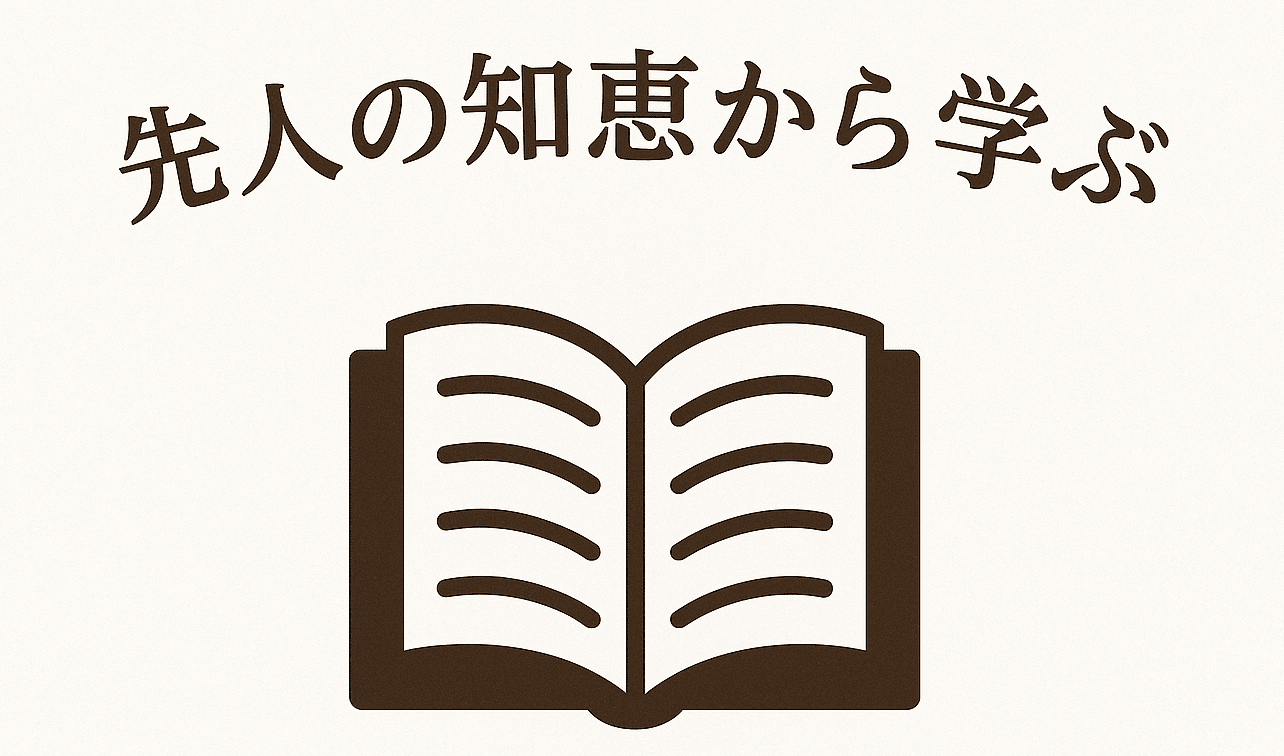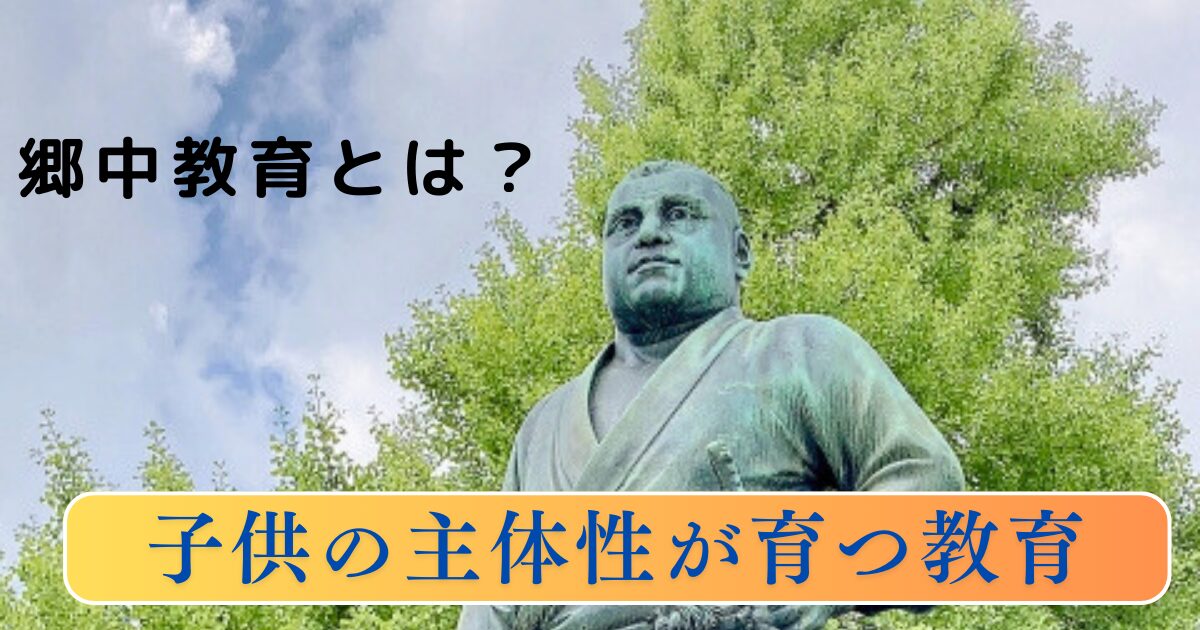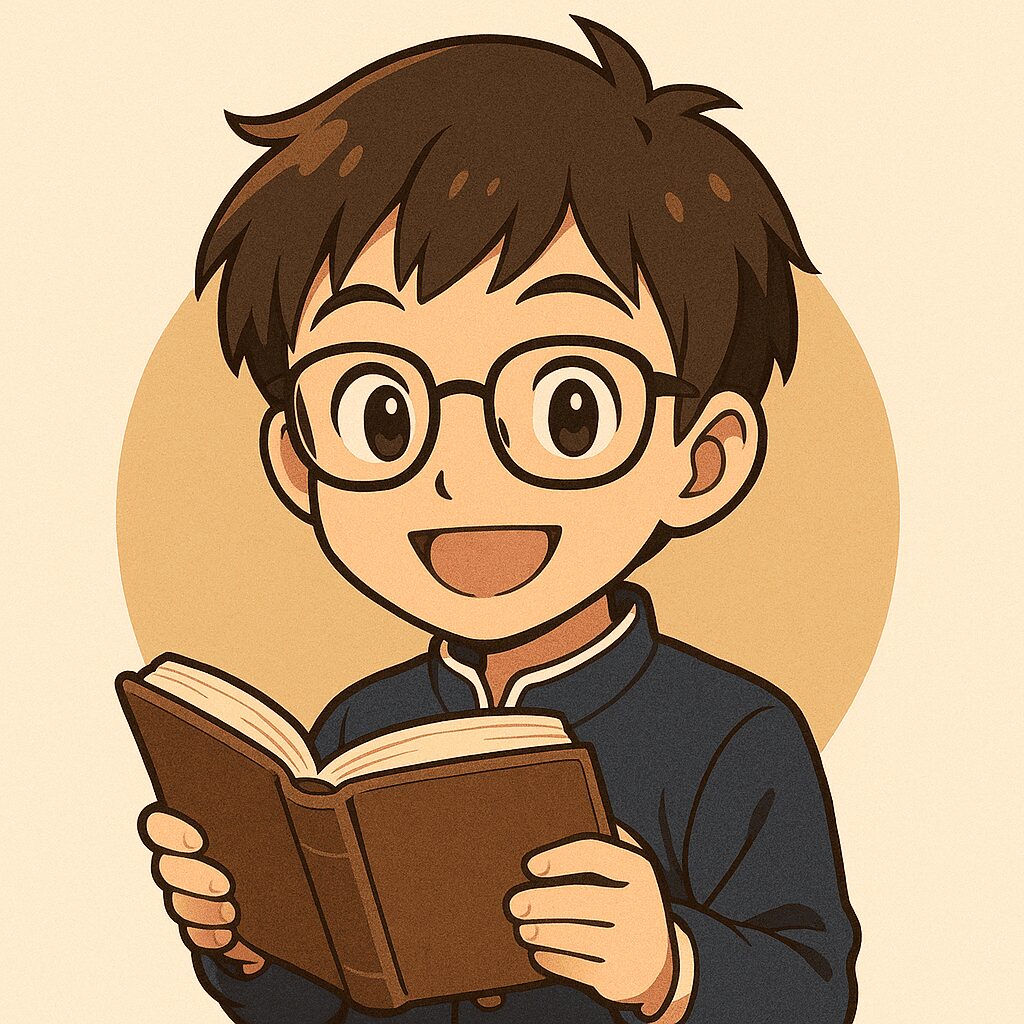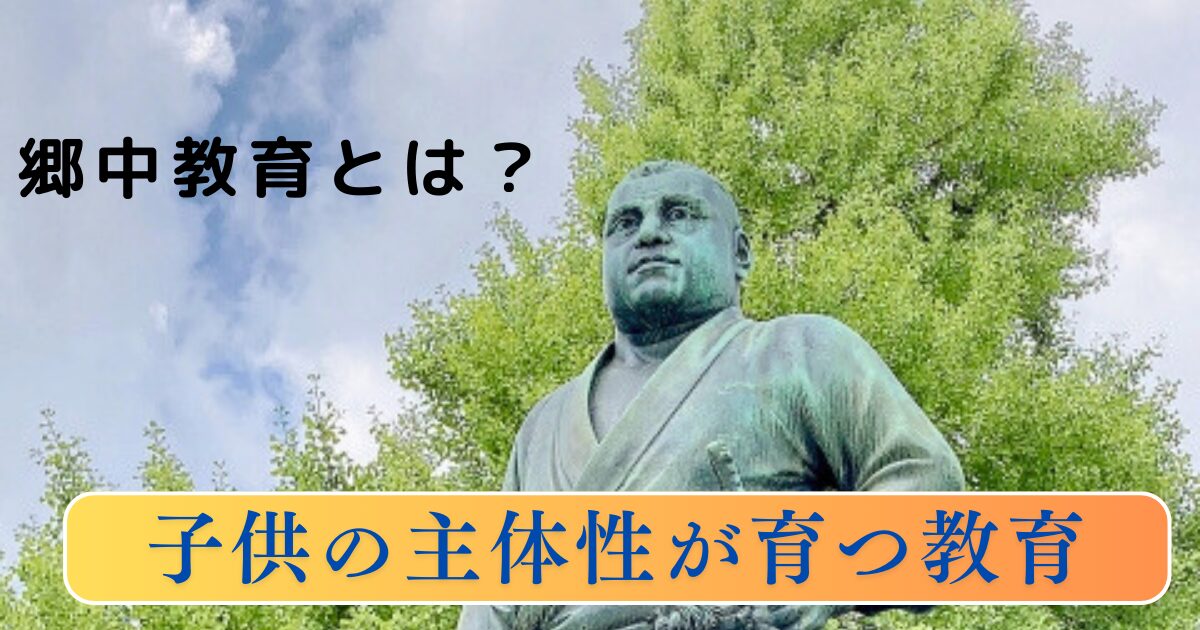
教えるのは先生や親(大人)学ぶのは生徒(子供) 現代では、当たり前の話しですよね。
実は、日本には昔から、子どもたちが自ら学び、教え合う教育スタイルがありました。
それが「郷中教育(ごじゅうきょういく)」です。
西郷隆盛や大久保利通、など多くの偉人を育てた教育法、実は今の時代でも通用すると思いました。
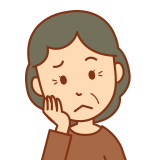
そもそも郷中教育って何ですか?

そんな方の悩みを解決いたします!
本記事では、郷中教育の特徴と現代教育への活かし方について、ご紹介します。
郷中教育とは?
郷中教育は、江戸時代中期の薩摩藩(現在の鹿児島県)で行われていた、地域密着型の教育システムです。
特徴は、子どもが子どもを育てる、大人は基本的に「見守る」スタイルでした。
具体的には、子どもたちは年齢によって以下のように役割分担されていました
- 小稚児(こちご):6~10歳
- 長稚児(おせちご):11~15歳
- 二才(にせ):15~25歳
- 長老(おせ):25歳以上
他にも、稚児頭、郷中頭(二才頭)、書物の師匠など役割がありました。

年上の子が年下の子を指導、年下の子は、年上の子から指導を受ける、その様子を地域の大人が見守る。
「学びの循環」が生まれていたのです。
学ぶ内容も幅広く、読み書きや儒学、武芸、そして「詮議(せんぎ)」と呼ばれる対話式の学びなど多様な方法が組み合わされていました。
【詮議】詮議には、通常の詮議と生活詮議があるとされていました。
- 通常の詮議:忠孝(ちゅうこう)と武士道を議題とした詮議
- 生活詮議:主に稚児の生活指導
子ども同士の学び合いが育む「主体性」
郷中教育は、教える事で学びになり、年長者が教える側に立つことで
- リーダーシップ:伝える力、導く力が身につく
- 責任感:教える立場としての自覚が芽生える
- コミュニケーション力:言葉を選び、相手に伝える力が磨かれる
- 主体性:教える必要があるので、何を教えたら良いのか自ら考える
また、「詮議」では、「問題に対してどうする?」という問いを投げ合いながら自分の意見を育て、他者の意見を尊重する姿勢が養われたとのこと
郷中教育の場では、失敗を咎めず挑戦することが推奨されていました。
※違反に対する罰は、存在していた可能性があります。
こうした「失敗を許容する空気」が、子どもの挑戦心と主体性を育てたのです。
郷中教育の名言
「負けるな 嘘をつくな 弱いものをいじめるな」
負けるな:人に負けないと言う事ではなく、自分に負けずあきらめないこと。
嘘をつくな:嘘をついたときには言い訳せず、素直に非を受け入れること。
弱い者をいじめるな:弱い者いじめは、器の小さい人間のすること。
•自分に負けない芯の強さ
•悪いことをしたら素直に謝る誠実さ
•弱い者いじめをしない優しさと小ささを咎める。
現代でも教育のスローガンとしても活用できそうですが、負けるなの意味が、誤った解釈で伝わらない様に、注意が必要だと思います。
郷中教育を現代に活かす方法と注意点
郷中教育は、現代の教育にも応用できます。
以下、具体的な3つの例と注意点を紹介します。
1. 上級生が下級生への勉強を教える
【例】上級生が下級生へ勉強を教える
異なる年齢の子どもが学び合うことで、上下の交流が生まれ自然とリーダーシップや協調性が育つ可能性があります。
【注意点】過度な上下関係の縦割りにならない様、大人が上級生にしっかりと指導する必要性があります。
下級生に対しても、上級生から学ぶ姿勢を教える必要があります。
2. 対話を重視した学び
郷中教育の「詮議」のように、子ども同士で考えを交わす場を作ることで、思考力や表現力が育つ可能性があります。
【例】他者の意見を重んじる、ディスカッション授業
【注意点】意見の対立が生じた際の解決策、他者の意見を尊重する考えを教える必要性があります。
3. 地域全体での見守りと支援
家庭だけでなく、地域が子どもの学びを見守る姿勢が大切です。
【例】地域の大人が学びの場に関わるボランティア制度
【注意点】誰でも子供を見守るボランティアに参加できるよりは、適格性を判断しボランティアに参加して貰えるとより安全性が増すと思います。
郷中教育は、人間力も育つ
郷中教育が教えてくれたのは、「学びは、循環するもの」だということ。
子どもたちが自分で考え、教え、支え合う環境があれば、知識だけでなく、人間力も育ちます。
地域と学校、家庭が手を取り合い、子どもたちが主役になれる学びの場を作る。
それこそが、これからの教育の理想形かもしれません。