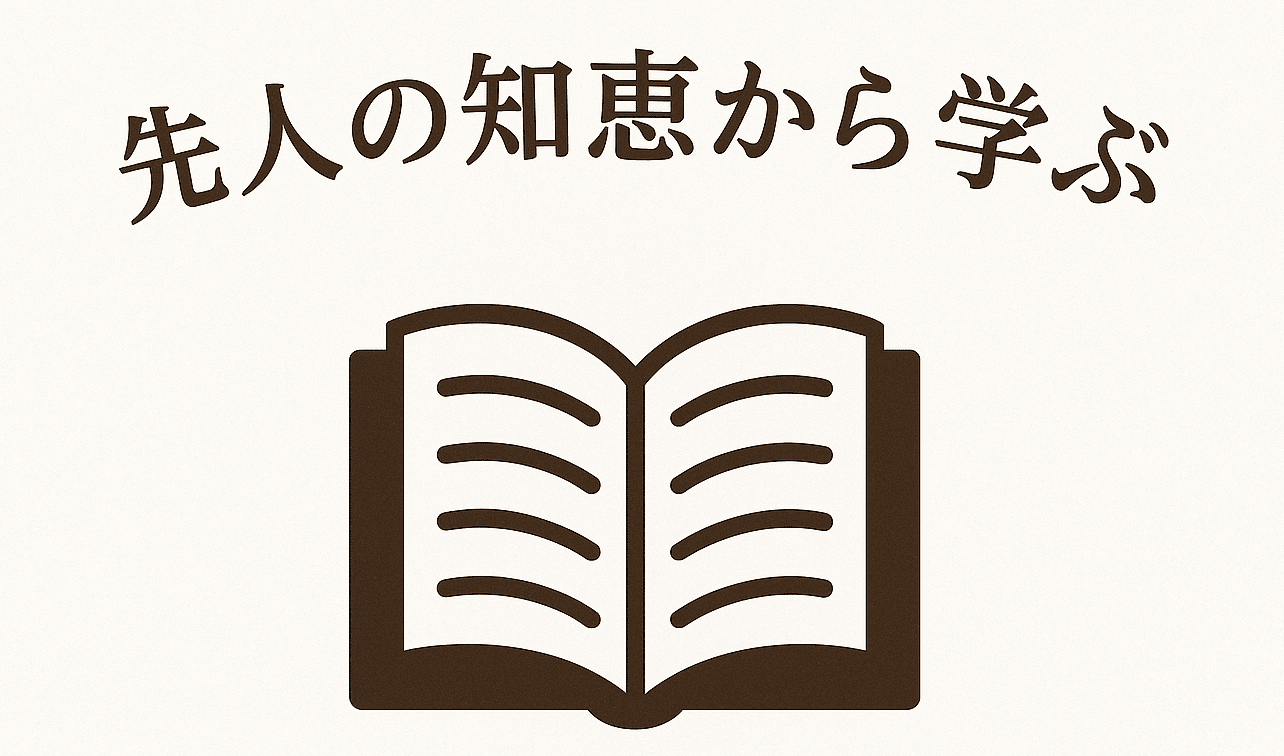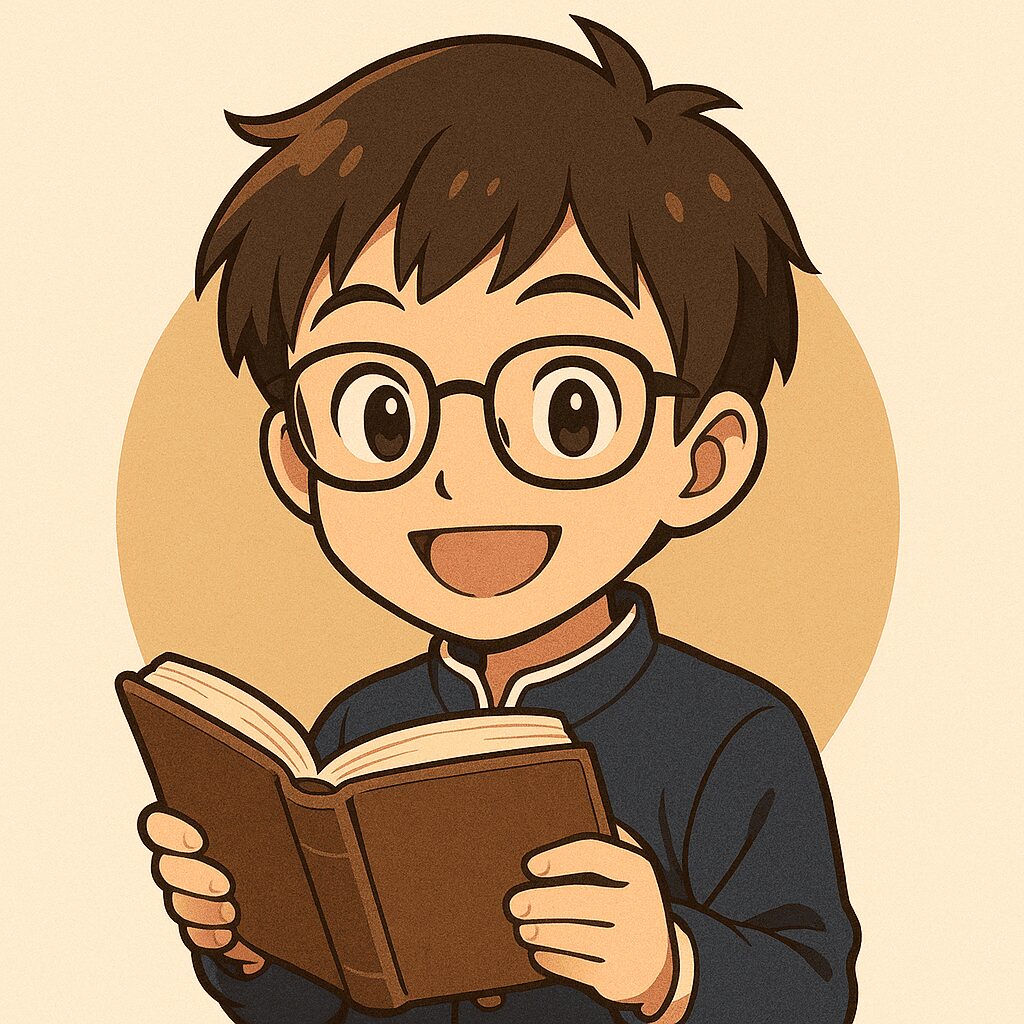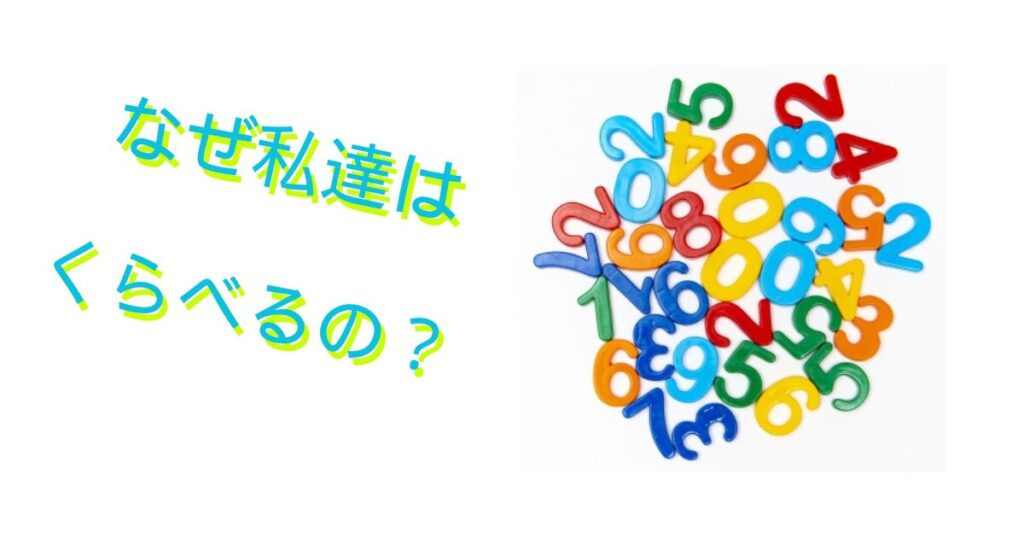
現代は、SNSやインターネットを通じて他者の生活や成功に日常的に触れる時代です。
その結果、私たちは無意識のうちに「自分と他人を比べる」という行動をとっています。
これを心理学では「社会的比較」と呼び、それに関する理論が社会的比較理論(Festinger,1954)という、心理学の考え方です。
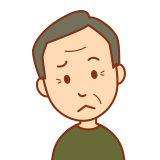
そんなこと知ったって比べられるし、比べてしまうよ。
その通りです。これから先も誰かと比べる、比べられる事は変わらないと思います。
ですが、この心理を理解しておくと心の健康やモチベーション管理にも役立ちます。
本記事では、社会的比較理論の概要から具体例、そして関連する心理モデルまで、わかりやすく解説していきます。
心理学に詳しくない方にも理解しやすい構成になっていますので、ぜひ参考にしてください。
社会的比較理論とは?
社会的比較理論は、アメリカの社会心理学者レオン・フェスティンガーによって1954年に提唱されました。
この理論の根本には「人は自分の能力や意見を正確に理解したい」という欲求があるとされています。
しかし、客観的な評価基準がないとき、多くの人は「他人との比較」によって自分の立ち位置を把握しようとします。
- 人は自己評価のために他者と比較する
- 評価基準が曖昧なとき、比較対象は「似た者同士」になりやすい
結論:他人と比べて落ち込むのは、むしろ自然なことです。
上方比較と下方比較とは?
【比較には2つのタイプがある】
- 上方比較(自分より上の人)
- 下方比較(自分より下の人)
■ 上方比較:自分よりも優れていると感じる人と比較すること
例: 成功している人を見て、「自分も頑張ろう」とモチベーションが上がる
→やる気が出る一方で、差が大きすぎると自信を失うリスクもある
■ 下方比較:自分よりも劣っていると感じる人と比較すること
例: 失敗したときに「もっと大変な人もいる」と思って気持ちを落ち着く
→自尊心を保ちやすくなるが、慢心や他者軽視につながる危険性もある
社会的比較の具体例〜SNS編〜
社会的比較は日常のさまざまな場面で行われています。
特にSNSでは、知らず知らずのうちに他者との比較が発生しています。
【よくある例】
• 上方比較:「あの人、いつもキラキラした生活してるな…私も頑張らないと」
• 下方比較:「この人も失敗してるんだ、なんか安心した」
他にも、「同級生の年収」「同僚の結婚生活」「友人の子育て」など、身近な話題すべてが比較の対象になり得ます。
自己評価維持モデルとは?社会的比較との関係
自己評価維持モデル(Self-Evaluation Maintenance Model)は、社会的比較理論を発展させた考え方のひとつです。
他者の優れた遂行を比較対象として、自己評価が上がることも下がる可能性もあります。
【例】自分よりも優れた同僚の成功を見聞きすることで、自分の能力が低いと感じ、自己評価が下がる可能性があります。
逆に優秀な同僚の成功に貢献したことで、自分の能力も高くなったと感じ、自己評価が上がる可能性もあります。
自己評価維持の強さには個人差があり、個人によっては、他者に影響を受けやすい傾向があります。
最後におさらい
- 社会的比較理論は「他者との比較」をテーマにした心理学の理論
- 上方比較・下方比較によってモチベーションや自尊心が影響を受ける
- 自己評価維持モデルは、より感情に近い比較の反応を説明
比較をやめる必要はありません。
その代わり、「比べてしまうのものなんだ」と優しく受け入れることで、心がきっとラクになります。
社会的比較理論は、現代人が自分を労るための「心のヒント」だと思います。
知っておいて損はないと思います。